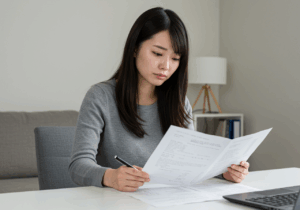離婚と不動産、財産分与のすべてを解説|損をしないための完全ガイド

目次
離婚時に知っておきたい「財産分与」の基本
離婚を考えるとき、避けて通れないのが財産分与です。特に、マイホームなどの不動産は高額な財産であるため、その扱いをめぐってトラブルになるケースが少なくありません。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合うことです。民法768条でも定められており、夫婦の一方が他方に対し、分与を請求する権利があります。
「専業主婦だったから財産分与は受けられないのでは…?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、財産形成への貢献は金銭的なものだけではなく、家事や育児も含まれます。そのため、基本的に専業主婦であっても財産分与の請求権は認められます。
財産分与の対象となる「共有財産」と対象外の「特有財産」
財産分与の対象となるのは、夫婦の協力によって形成された共有財産です。具体的には、以下のようなものが該当します。
- 婚姻中に購入した不動産(マイホーム、土地など)
- 預貯金、現金
- 株式や債券などの有価証券
- 生命保険や学資保険の解約返戻金
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)
- 年金(厚生年金・共済年金)
一方、夫婦が協力して築いたとは言えない特有財産は、財産分与の対象外となります。
- 婚姻前から所有していた財産(預貯金、不動産など)
- 婚姻中に相続や贈与によって得た財産
例えば、親から相続した土地に家を建てた場合、土地部分は特有財産ですが、その上に建てた建物は共有財産と見なされるケースが多いです。どこまでが共有財産で、どこからが特有財産なのか判断が難しい場合もあるため、詳しくは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
不動産は「時価評価」が鍵!査定額の重要性
不動産を財産分与する場合、まずその時価評価額を算出する必要があります。時価評価とは、現時点でその不動産を売却した場合にいくらになるかを算定することです。この時価評価額を基準に、分与の方法や金額が決まります。
不動産の時価を調べる方法
不動産の時価を調べるには、主に以下の方法があります。
- 不動産会社に査定を依頼する最も一般的な方法です。複数の不動産会社に査定を依頼し、その平均値や中央値を参考にすると、より正確な時価を把握できます。
- 不動産鑑定士に鑑定を依頼する不動産鑑定士は、専門的な知見から不動産の価値を評価します。鑑定書は裁判などでも有効な証拠となりますが、費用が高額になる傾向があります。
- インターネットの一括査定サイトを利用する手軽に複数の不動産会社の査定額を知ることができます。おおよその相場を把握したい場合に便利です。
査定を依頼する際は、査定額の根拠(周辺の取引事例など)をしっかり確認することが大切です。夫婦それぞれが別の不動産会社に査定を依頼し、査定額に開きがある場合は、その差をどう埋めるかが離婚協議のポイントになります。
「固定資産税評価額」は財産分与の基準にならない?
「固定資産税の通知書に書いてある評価額を使えばいいのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、これは適切ではありません。固定資産税評価額は、あくまで税金を計算するために市町村が独自に定めたものであり、実際の市場価格(時価)とは大きく異なるケースが多いためです。財産分与においては、時価評価額を基準にするのが原則です。
不動産にまつわる問題|「住宅ローン」と「オーバーローン」
不動産の財産分与で最も複雑になりやすいのが、住宅ローンが残っているケースです。特に、不動産の時価がローン残高を下回る「オーバーローン」の状態だと、より慎重な検討が必要となります。
住宅ローンが残っている場合の基本的な考え方
住宅ローンは、夫婦の協力によって築いた財産ではなく、夫婦の負債です。そのため、財産分与の際には、不動産の時価からローン残高を差し引いた金額を分与の対象とします。
【計算式】
不動産の評価額 - 住宅ローン残高 = 財産分与の対象となる財産額
この計算の結果、プラスになれば財産分与の対象となり、マイナスになればオーバーローンの状態となります。
「オーバーローン」だった場合の対処法
オーバーローンとは、不動産の売却額(時価)よりも住宅ローンの残債が多い状態のことです。この場合、不動産を売却してもローンを完済できず、手元に財産が残りません。
【オーバーローンの例】
- 不動産の時価:2,000万円
- 住宅ローン残高:2,500万円
- 差額:-500万円
このような場合、分与するべき財産がないため、夫婦間で特別な取り決めをしない限り、財産分与の対象とはなりません。しかし、家を売却すると不足分を補填する必要が生じます。この不足分をどのように負担するかは、夫婦の話し合いで決める必要があります。
不動産の財産分与|具体的な3つの方法と手続き
不動産を財産分与する方法は、主に以下の3つが挙げられます。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、夫婦の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
1. 不動産を「売却」して現金を分ける(換価分割)
不動産を売却し、得られた代金からローン残高や諸費用を差し引いた残りを、夫婦で分け合う方法です。
- メリット:
- 公平に分けやすい
- 後々のトラブルを避けやすい
- 現金化できるため、それぞれが新たな生活を始める資金にできる
- デメリット:
- 手続きに手間と時間がかかる
- 売却益が発生した場合、税金がかかる可能性がある
- 子どもの生活環境が変わってしまう
売却の手続きには、査定、不動産会社との契約、購入者探し、引き渡しなど、多くのプロセスがあります。詳細は、売却手続きに関する専門的な情報も参考にすると良いでしょう。
2. どちらかが家に住み続け、相手に「金銭を払う」(代償分割)
どちらか一方が不動産に住み続け、その代わりに相手に相当額の金銭を支払う方法です。これを代償金と呼びます。
- メリット:
- 子どもの生活環境を変えずに済む
- 住み慣れた家に住み続けられる
- デメリット:
- 代償金を支払う側に支払い能力が必要
- 代償金の額や支払い方法について合意が必要
- 住宅ローンの名義変更や借り換えが必要になる場合がある
代償金の額は、不動産の時価を基準に話し合って決定します。この方法を選択する場合、離婚協議書で代償金の額や支払い期日、方法などを明確に定めておくことが非常に重要です。
3. 不動産をそのまま分け合う(現物分与)
不動産の持分割合を変更することで、不動産を夫婦で共有し続ける方法です。例えば、夫名義だった不動産の持分を妻に一部譲渡する、といった形です。
- メリット:
- 売却や代償金の支払いが不要
- デメリット:
- 離婚後も元夫婦で不動産を共有することになるため、管理や維持費などでトラブルになりやすい
- 将来的に売却する際も、元夫婦で協力する必要がある
この方法は、あまり一般的な選択肢ではありません。不動産トラブルを避けるためにも、できる限り避けることをおすすめします。
離婚後の不動産トラブルを避けるためのポイント
不動産をめぐるトラブルを未然に防ぐためには、いくつかの重要なポイントがあります。
1. 「離婚協議書」の作成は必須!
離婚協議書は、財産分与や慰謝料、養育費など、離婚に際して取り決めた内容をまとめたものです。特に不動産の財産分与については、以下の点を明確に記載しましょう。
- 不動産の分与方法(売却、代償分割など)
- 不動産の名義変更や売却手続きにかかる費用負担
- 代償金の額、支払い期日、支払い方法
- 住宅ローン残高の負担方法
この離婚協議書を公正証書にすることで、法的拘束力を持たせることができます。公正証書にすることで、万が一、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに強制執行が可能になります。
離婚協議書について、詳しくは当サイトのトップページ(https://rikon.houmu.online/)もご参照ください。
2. 「財産隠し」に注意!
相手が財産を隠しているのではないかと疑うケースも少なくありません。特に、離婚を切り出された後、不動産や預貯金の名義をこっそり変更されるといった財産隠しのリスクがあります。
疑わしい場合は、弁護士などの専門家に相談し、相手の財産調査を依頼することも可能です。
3. 専門家への相談を積極的に
財産分与は、専門的な知識が必要な場合が多く、ご自身だけで解決しようとすると不利な条件で合意してしまう可能性があります。
- 弁護士:法律の専門家として、法的な観点からアドバイスや交渉、訴訟代理を行います。
- 行政書士:離婚協議書の作成など、書類作成の専門家です。
当サイトの運営者は行政書士です。料金プランはサービス内容ページ(https://rikon.houmu.online/service/)をご確認ください。
疑問や不安な点があれば、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみましょう。当サイトのお問い合わせフォーム(https://rikon.houmu.online/contact/)からご連絡いただければ、ご相談を承ります。
離婚と不動産|よくある質問
Q. 離婚後、夫名義の家に住み続けられますか?(家の居住権)
原則として、法律上の居住権というものは存在しません。そのため、名義人である夫(または妻)が「出て行ってほしい」と言えば、退去しなければならないのが一般的です。
しかし、夫婦の合意によって、離婚後も一定期間住み続けることを認められるケースもあります。この場合も、口約束ではなく、必ず離婚協議書にその旨を記載しておくことが大切です。
Q. 財産分与の請求には期限がありますか?
はい、あります。民法768条2項では、「離婚の時から2年以内」に請求しなければならないと定められています。離婚後、時間が経つほど不動産の価値も変動するため、できるだけ早く話し合いを進めることが重要です。
Q. 離婚で不動産を売却した場合、税金はかかりますか?
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。しかし、自宅を売却する場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」など、様々な税金の優遇措置が適用できる可能性があります。
特例の適用には条件がありますので、詳しくは税理士などの専門家や最寄りの税務署に確認することをおすすめします。
離婚と不動産に関する専門家への相談
離婚に際して、不動産の財産分与で悩むことは少なくありません。特に、住宅ローンや子どもの住まいなど、デリケートな問題が絡み合うため、精神的な負担も大きいことでしょう。
ご自身の状況に応じて、最も良い選択肢を見つけるためにも、専門家の力を借りることは非常に有効です。当サイトの運営者は行政書士として、皆さまの新たな一歩をサポートしています。当事務所について詳しく知りたい方は、ホームページ運営者(行政書士)の事務所情報ページ(https://rikon.houmu.online/about/)をご覧ください。
このブログ記事を読んで、少しでも不安が和らぎ、前向きに問題解決に取り組むきっかけとなれば幸いです。
参考文献・参考サイト
- 法務省 - 財産分与についてhttps://www.moj.go.jp/minji/minji07_00007.html財産分与の基本的な考え方について、法律的な側面から解説されています。
- 国土交通省 - 不動産に関する税金https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000021.html不動産売却にかかる税金について、詳細な情報が掲載されています。
- All About - 財産分与https://allabout.co.jp/gm/gc/25927/具体的な財産分与の事例や計算方法などが、分かりやすく解説されています。
- SUUMO - 離婚時の不動産売却https://suumo.jp/journal/2021/04/16/180293/不動産売却の流れや注意点について、不動産情報サイトならではの視点で解説されています。
- LIFULL HOME'S PRESS - 離婚で家はどうなる?https://www.homes.co.jp/cont/press/estate/estate_00832/離婚と不動産に関するQ&A形式で、様々な疑問に答えています。
※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。