離婚協議書を自分で作成したいあなたへ。完全ガイドとテンプレート、注意点を徹底解説
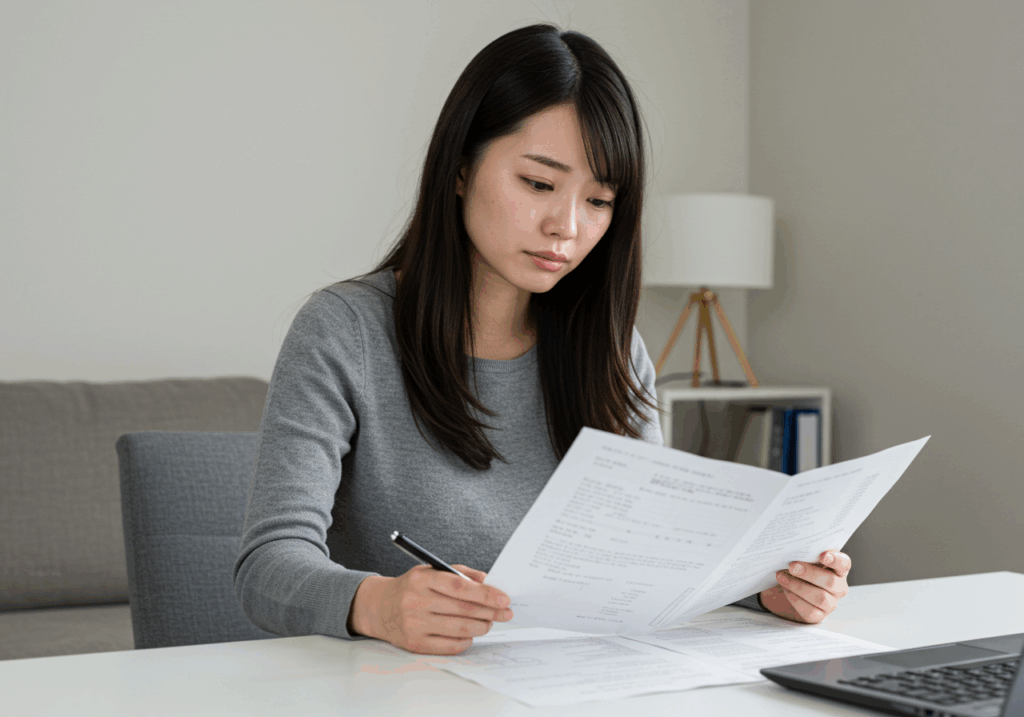
離婚協議書は、離婚後の生活を左右する重要な書類です。弁護士や行政書士に依頼する選択肢もありますが、「できるだけ費用を抑えたい」「自分で作成して内容をしっかり把握したい」と考える方も多いでしょう。この記事では、離婚協議書を自分で作成するための具体的な手順から、押さえておくべき法的効力、テンプレートの活用方法まで、詳細に解説します。
目次
離婚協議書はなぜ必要? 作成するメリットとデメリット
「口約束でもいいのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは大きなリスクを伴います。離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐために不可欠な書類です。
離婚協議書を作成する3つのメリット
- 将来のトラブルを防止する口約束では「言った、言わない」の水掛け論になりがちです。特に養育費や財産分与などは、金額や支払い方法で後々トラブルに発展するケースが少なくありません。書面に残すことで、お互いの約束を明確にし、紛争を防ぐことができます。
- 法的な証拠になる公正証書化していなくても、夫婦の合意を証明する重要な証拠となります。もし相手が約束を守らなかった場合、この書面を基に話し合いを進めたり、調停や裁判の際に証拠として提出したりできます。
- 安心感を得られる書面として残すことで、精神的な安心感にもつながります。「これで養育費の支払いは大丈夫」「財産分与についてきちんと決めることができた」と、離婚後の生活を前向きにスタートさせるための土台となります。
自分で作成するデメリット
一方で、自分で作成することにはデメリットも存在します。
- 不備があると無効になる可能性がある法的知識がないまま作成すると、内容に不備があり、後で約束を破られた際に有効な証拠とならない可能性があります。例えば、養育費の金額が曖昧だったり、支払期間が明確でなかったりすると、後々問題になります。
- 交渉に感情が入り込みやすい夫婦間で直接交渉すると、感情的になり、冷静な話し合いが難しくなることがあります。専門家が間に入ることで、公平な視点からスムーズな交渉が可能です。
- 時間と手間がかかるインターネットで情報を集め、テンプレートを探し、内容を吟味し、交渉する。これら全てを一人で行うには、かなりの時間と労力を要します。
離婚協議書作成の手順:自分で作るときの具体的なステップ
離婚協議書の作成手順は、次の5つのステップに沿って進めます。
- 話し合うべき項目を洗い出すまずは、夫婦で話し合って決めるべきことをリストアップします。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用
- その他(今後の連絡方法など)
- 夫婦間で話し合い、条件を合意する洗い出した項目について、夫婦で話し合い、一つひとつ合意形成を図ります。感情的にならず、冷静に話し合うことが重要です。話し合いが難しい場合は、第三者を間に入れることも検討しましょう。
- テンプレートやひな形を活用して草案を作成する合意した内容を元に、離婚協議書テンプレートやひな形を使って草案を作成します。インターネット上には、無料でダウンロードできる離婚協議書ひな形無料のサイトが多数存在します。【テンプレート選びのポイント】
- 必要な項目が網羅されているか
- 記載例や解説が付いているか
- シンプルな書式で、自分で編集しやすいか
- 内容を最終確認する草案ができたら、誤字脱字がないか、また、夫婦で合意した内容が正確に反映されているかを最終確認します。特に金額や日付、氏名、住所などは慎重にチェックしましょう。
- 署名・捺印する夫婦双方が内容に納得したら、原本を2通作成し、それぞれが署名・捺印します。これにより、離婚協議書は完成です。原本は、夫婦それぞれが1通ずつ保管します。
必ず記載すべき必須項目と書き方・記載例
離婚協議書に記載すべき項目は多岐にわたりますが、特に重要な項目とその書き方・記載例を詳しく見ていきましょう。
1. 離婚の合意
まず、夫婦が協議離婚に合意したことを明確に記載します。
- 記載例: 「〇〇(夫)と〇〇(妻)は、協議離婚することに合意し、本契約を締結する。」
2. 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、親権指定方法を明確に記載します。
- 記載例: 「長男〇〇(生年月日)の親権者は、妻〇〇と指定する。」
3. 養育費の取り決め
養育費の取り決めは、子どもの将来に直結する重要な項目です。
- 記載すべき項目:
- 金額
- 支払い期間(「〇〇が満20歳に達するまで」など)
- 支払い方法(「毎月〇〇日までに、〇〇銀行の口座に振込」など)
- 記載例: 「夫は、長男〇〇の養育費として、月額〇〇円を、〇〇が満20歳に達する月まで、毎月末日までに妻〇〇が指定する口座に振り込む方法で支払う。」
4. 面会交流条件
面会交流条件は、子どもの健全な成長のために不可欠です。
- 記載すべき項目:
- 頻度(「月に1回」「年2回」など)
- 方法(「子どもが合意した場合のみ」など)
- 場所、日時
- 記載例: 「面会交流は、月に1回程度、〇〇と長男〇〇が話し合って日時・場所を決定する。」
5. 財産分与
財産分与書式は、具体的に財産を特定し、どのように分与するかを明確に記載します。
- 記載すべき項目:
- 分与対象の財産(現金、預貯金、不動産、自動車など)
- 分与方法、金額
- 記載例: 「夫婦共有財産である〇〇銀行普通預金口座の預金〇〇円は、夫〇〇が取得するものとする。」
6. 慰謝料
不貞行為など、慰謝料が発生する原因がある場合は、慰謝料記載例を参考に明確に記載します。
- 記載すべき項目:
- 金額
- 支払い方法、期日
- 記載例: 「夫〇〇は、不貞行為に基づく慰謝料として、妻〇〇に対し、金〇〇円を、〇〇年〇〇月〇〇日限り、妻〇〇が指定する口座に振り込む方法で支払う。」
7. 清算条項
清算条項は、記載された項目以外に請求権がないことを確認する重要な項目です。
- 記載例: 「甲と乙は、本契約に定める事項以外に、互いに金銭その他いかなる名目の債権債務がないことを確認する。」
離婚協議書の法的効力と公正証書化
離婚協議書は、夫婦間の合意を証明する重要な書面ですが、公正証書にすることで、さらに強力な法的効力を持つことができます。
離婚協議書は公正証書にすべき?
公正証書にすると、次のようなメリットがあります。
- 強制執行が可能になる公正証書には、養育費や慰謝料の支払い義務を定めた場合、「強制執行認諾約款」を付すことで、万一相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに強制執行(給料差し押さえなど)を行うことができます。
- 高い証明力を持つ公証役場で公証人が作成するため、記載内容が正確であり、高い証明力を持ちます。
- 原本が公証役場に保管される紛失の心配がなく、いつでも再発行が可能です。
公正証書化する方法
公正証書化するには、夫婦で公証役場に出向き、離婚協議書の内容を公証人に伝えて作成してもらいます。
公正証書化の費用は、取り決める内容によって異なりますが、一般的には数万円から10万円程度です。
離婚協議書作成でよくあるQ&A
Q1. 手書きでも大丈夫?
はい、離婚協議書手書きでも問題ありません。ただし、読みやすく、間違いのないように丁寧に記載しましょう。パソコンで作成したものを印刷して、署名・捺印する方法が一般的です。
Q2. どこで相談できる?
弁護士や行政書士に相談することができます。弁護士は法律相談や相手との交渉代理、調停・裁判の手続きを任せることができます。行政書士は、書類作成の専門家として、離婚協議書の作成をサポートしてくれます。
当サイトは行政書士が運営する離婚協議書作成代行サービスです。ご相談も承っておりますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
Q3. 離婚協議書作成の費用はどのくらい?
自分で作成すれば、費用はかかりません。ただし、公正証書にする場合は、公証人手数料が発生します。専門家に依頼する場合の離婚協議書作成費用は、依頼する専門家や内容によって異なりますが、数万円から十数万円が相場です。当サイトの料金プランも参考にしてください。https://rikon.houmu.online/service/
Q4. 離婚協議書作成で失敗しないためのポイントは?
- 感情的にならない冷静に話し合い、お互いが納得できる内容にすることが大切です。
- 曖昧な表現を避ける「適宜」「適当に」といった曖昧な言葉は使わず、金額や日付など、具体的な数値を記載しましょう。
- 全ての項目を網羅する「もう決まったからいいや」と安易に思わず、今後の生活で必要になるかもしれない項目は全て洗い出し、話し合いましょう。
- 専門家への相談を検討する少しでも不安がある場合は、専門家へ相談することをおすすめします。当サイトの運営者である行政書士事務所情報もご確認ください。https://rikon.houmu.online/about/
離婚後のトラブルを防止するために
離婚は、人生の大きな転機です。離婚協議書は、この転機を乗り越え、新しい人生を円滑にスタートさせるための羅針盤のようなものです。自分で作成することで、内容を深く理解し、責任を持って今後の生活を送る覚悟にもつながります。
もちろん、一人で全てを抱え込む必要はありません。もし、離婚条件トラブル防止のためにも、専門家のサポートが必要だと感じたら、いつでもご相談ください。あなたの新しい一歩を、心から応援しています。
当サイトの最新のブログ記事はこちらからご覧いただけます。ぜひ参考にしてください。
参考URL
- 日本弁護士連合会
- 弁護士を検索できるデータベースです。
- https://www.nichibenren.or.jp/
- 法務省
- 離婚に関する法制度や手続きについて解説しています。
- https://www.moj.go.jp/
- 日本公証人連合会
- 公証役場の場所や公正証書に関する情報が掲載されています。
- https://www.koshonin.gr.jp/
- 厚生労働省
- ひとり親家庭に対する支援制度や養育費に関する情報があります。
- https://www.mhlw.go.jp/
- 裁判所
- 離婚調停や裁判の手続きについて詳細が確認できます。
- https://www.courts.go.jp/
- 日本行政書士会連合会
- 行政書士の役割や相談窓口について情報が提供されています。
- https://www.gyosei.or.jp/
※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

