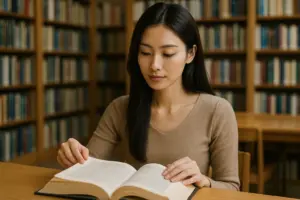離婚せず別居する生活費の不安を解消!婚姻費用から公正証書まで徹底解説

「離婚はしたくないけど、別居したい…」。そう考えているあなた。別居中の生活費、どうなるんだろうと不安に感じていませんか?
生活費は、別居する上で最も重要な問題の一つです。特に、専業主婦や収入に差がある場合、生活費が途絶えてしまうのではないかと心配になりますよね。
この記事では、離婚せずに別居する際の生活費、通称「婚姻費用」について、その基礎から具体的な手続き、注意点まで詳しく解説します。
目次
婚姻費用とは?別居中の生活費の基礎知識
まず、別居中の生活費を考える上で、絶対に押さえておきたいのが「婚姻費用分担請求」という概念です。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。これには、衣食住の費用、医療費、教育費、交際費、娯楽費などが含まれます。
そして、民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。これは、夫婦のどちらかが別居しても、この義務は変わらないことを意味します。
つまり、夫婦の収入に差がある場合、収入の多い方が少ない方に対して、生活費を分担する義務があるのです。これが「婚姻費用分担請求」です。
別居の定義:生活費請求のスタートライン
「別居」と聞くと、物理的に家を出て、まったく連絡を取らない状態を想像するかもしれません。しかし、法的な観点では、必ずしも厳密な線引きがあるわけではありません。
一般的には、夫婦が共同生活の基盤を失い、別々に生活している状態を指します。たとえ同じ家の中にいても、夫婦としての共同生活が破綻していれば「別居」と見なされるケースもあります。
別居中の生活費相場は?婚姻費用算定表をチェック
「で、結局いくらもらえるの?」
多くの方が最も知りたいのが、この金額ではないでしょうか。
婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子どもの年齢・人数によって異なります。この金額を算定するために、裁判所の実務で広く使われているのが「婚姻費用算定表」です。
この算定表は、裁判官や弁護士が婚姻費用を計算する際の目安として作成されたもので、夫婦双方の年収と子どもの人数・年齢を当てはめるだけで、おおよその婚姻費用が分かります。
婚姻費用算定表の見方
算定表は、夫婦それぞれの収入と子どもの人数・年齢に応じて、複雑な計算式を簡略化したものです。
| 義務者(支払い側)の収入 | 権利者(受け取り側)の収入 | 婚姻費用 | |
| 例1:子ども1人(0歳~14歳)の場合 | 夫:給与所得500万円 | 妻:給与所得150万円 | 月額約10万~12万円 |
| 例2:子ども2人(0歳~14歳、15歳以上)の場合 | 夫:給与所得700万円 | 妻:給与所得0円(専業主婦) | 月額約18万~20万円 |
| 例3:子どもなしの場合 | 夫:給与所得400万円 | 妻:給与所得100万円 | 月額約8万~10万円 |
※上記はあくまで目安です。実際の算定表はより詳細に分かれています。
この表を見れば、ご自身の状況に近いケースで、どのくらいの生活費がもらえるのか、大まかな別居中の生活費相場を把握することができます。
正確な金額を知りたい場合は、ご自身の年収や源泉徴収票などを用意して、弁護士に相談してみることをお勧めします。
婚姻費用を確実に受け取るための手続き
口約束だけでは、「言った、言わない」の水掛け論になりかねません。婚姻費用を確実に受け取るためには、きちんと法的な手続きを踏むことが重要です。
1. 別居開始の通知と請求
別居を始める前に、まずは相手に別居の意思と婚姻費用分担の意思を伝えることが大切です。
この際、口頭ではなく、内容証明郵便などを利用して書面で通知することで、後々のトラブルを防ぐことができます。書面には、別居開始通知と婚姻費用分担の請求を明確に記載しましょう。
2. 夫婦間の話し合いと公正証書の作成
相手が婚姻費用の支払いに応じる場合、まずは夫婦間で話し合いを行います。金額、支払い方法、支払期日などを具体的に決めましょう。
話し合いで合意ができたら、その内容を公正証書にすることをおすすめします。公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
| 公正証書作成のメリット | 公正証書作成のデメリット | |
| メリット | 支払い義務の履行が確実になる<br>→ 相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに強制執行手続が可能<br>証拠能力が高い<br>→ 後々のトラブルや裁判で有力な証拠となる | 作成費用がかかる<br>→ 数万円~10万円程度が相場<br>相手の協力が不可欠<br>→ 相手が公正証書作成に同意しないと作成できない |
公正証書を作成しておけば、相手が支払い拒否対応をしても、給料や預貯金などを差し押さえる「強制執行手続」をすぐに行うことができます。
3. 家庭裁判所での手続き(調停・審判)
話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停申立ての流れ
- 申立書の作成・提出
- 調停期日の設定
- 調停委員を交えた話し合い
- 調停成立
調停では、調停委員が夫婦双方の言い分を聞き、解決策を探ります。しかし、調停でも合意に至らない場合は、「審判」に移行します。
審判では、裁判官が夫婦の状況を考慮し、婚姻費用の金額などを決定します。この審判は法的拘束力を持つため、相手は審判で決定された金額を支払う義務が生じます。
これらの手続きを一人で行うのは非常に大変です。弁護士に相談することで、必要な書類の準備や手続きをスムーズに進めることができます。
収入格差や共働きの場合の注意点
配偶者との収入格差が大きい場合
夫婦の収入に大きな差がある場合、婚姻費用の金額も高くなる傾向があります。しかし、相手が「そんなに払えない」と主張してくることもあります。
このような場合、相手の収入証明(源泉徴収票や確定申告書など)を提出してもらうことが重要です。相手が収入を隠そうとする場合は、弁護士を通じて開示を求めることも可能です。
共働き夫婦の別居
「共働き別居」の場合、婚姻費用は発生しないと思われがちですが、そうではありません。
夫婦それぞれの収入に差があれば、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求できます。
ただし、夫婦の収入が同程度であれば、婚姻費用は発生しないか、非常に少ない額となる可能性が高いです。
また、「別居と養育費」も重要な論点です。婚姻費用には、子どもにかかる費用(教育費や養育費)も含まれます。
しかし、別居後に離婚が成立し、親権者が決定すると、婚姻費用ではなく養育費の支払い義務が生じます。養育費も、婚姻費用と同様に算定表を元に金額が決められます。
実家へ別居する場合
「実家だから生活費がかからないでしょ?」と相手に言われることもあります。
しかし、実家別居生活費も婚姻費用に含まれます。実家での生活費は、家賃や食費などがかからない分、一人暮らしより安くなることは事実です。しかし、生活費がゼロになるわけではありません。
この場合も、算定表を元に金額を算定することが基本となります。相手の主張に惑わされず、正当な婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用の証拠と記録の重要性
婚姻費用の請求や調停申立てを行う際、生活費の証拠は非常に重要です。
- 家計簿:日々の生活費の支出を記録しておきましょう。
- 預金通帳:生活費がどのように使われたかを示す証拠になります。
- クレジットカードの利用明細:支出の記録として使えます。
- LINEやメールのやりとり:相手が婚姻費用の支払いを拒否したり、話し合いに応じなかったりした際の重要な証拠になります。
特に、LINEで請求することは、手軽で記録が残るため、有効な手段の一つです。
弁護士に相談するメリット
ここまで、別居中の生活費について見てきましたが、一人でこれらの手続きを進めるのは非常に大変です。
弁護士相談には、以下のようなメリットがあります。
- 正確な婚姻費用の算定
- 相手との交渉の代行
- 調停や審判の手続き代行
- 法的アドバイス
- 精神的なサポート
特に、相手が話し合いに応じない、収入を隠す、といったケースでは、弁護士の存在は非常に心強いものです。
離婚はしないけど別居する?別居の目的と生活水準
「離婚はしたくないけど、別居したい」という選択は、決して珍しいことではありません。
夫婦の関係を修復したい、お互いに冷静になる時間が必要、といった理由で別居を選ぶ人もいます。
しかし、別居中の生活は、必ずしも元の生活水準が維持できるわけではありません。婚姻費用は、あくまでも生活を維持するための費用であり、贅沢をするためのものではないからです。
また、別居期間が長くなると、相手に離婚の意思がない場合でも、離婚を望む側から「別居調停」を申し立てられる可能性も出てきます。
そして、最終的に離婚することになった場合、「財産分与準備」も必要になってきます。別居中に夫婦の財産を把握し、リストアップしておくことが重要です。
SNS相談体験談から見る別居生活費のリアル
SNS上には、「SNS相談体験」として、別居中の生活費に関する悩みが多数投稿されています。
- 「夫が生活費を払ってくれない。どうしたらいい?」
- 「婚姻費用の調停を申し立てたいけど、やり方が分からない」
- 「実家に帰ったけど、お金がなくて困っている」
このように、多くの人が同じような悩みを抱えています。
もしあなたが同じような状況に直面しているなら、一人で抱え込まず、専門家や同じ悩みを持つ人に相談してみるのも良いでしょう。
「別居子どもサポート」として、行政やNPOが行っている支援もありますので、活用してみることも検討してください。
一人で悩まずに、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、初回相談を無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
参考URL
- 裁判所「養育費・婚姻費用算定表」婚姻費用を計算するための算定表が掲載されています。https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santeihyo/index.html
- 法務省「公正証書」公正証書の内容や作成方法について詳しく解説されています。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
- 内閣府男女共同参画局「婚姻費用の分担について」婚姻費用の基本的な考え方や、夫婦間の協力義務について説明されています。https://www.gender.go.jp/kaikaku/shingikai/sankou/pdf/danjokyoudou12_shiryo5.pdf
- 弁護士ドットコム弁護士が監修した、婚姻費用に関するコラムやQ&Aが豊富に掲載されています。https://www.bengo4.com/c_1003/c_1333/
- 日本司法支援センター(法テラス)無料法律相談や弁護士費用の立替え制度について案内されています。https://www.houterasu.or.jp/
※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。