離婚協議書を公正証書にする費用はいくら?相場と手続きを徹底解説
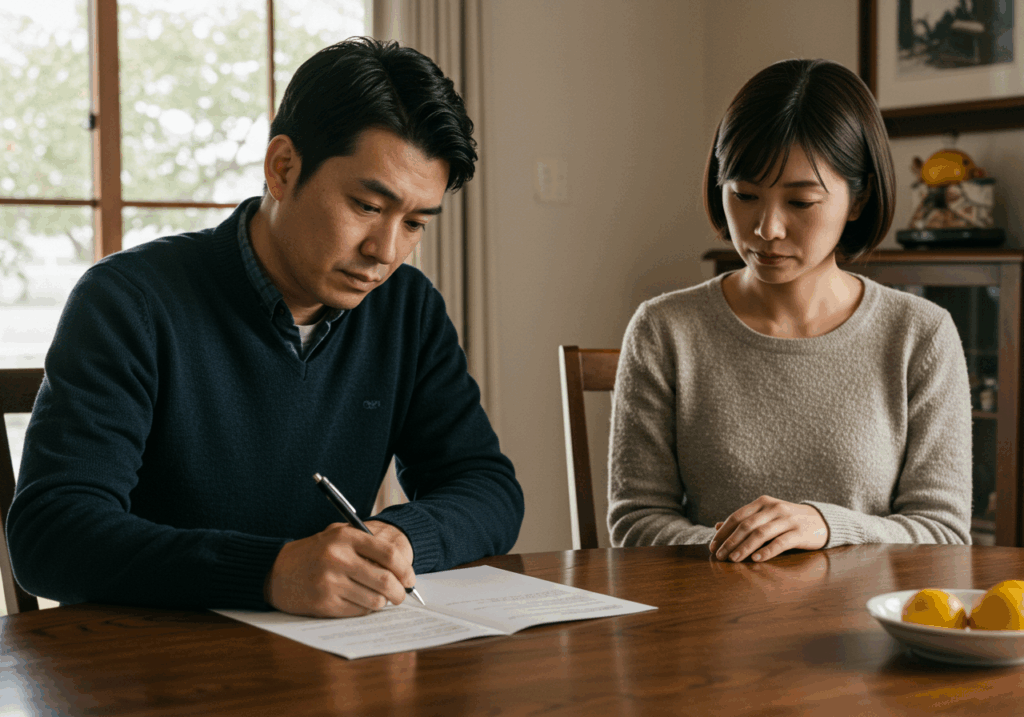
離婚を考え始めたとき、まず頭に浮かぶのは「これからどうなるんだろう?」という漠然とした不安ではないでしょうか。特に、お金のこと、子どものこと、住まいのことなど、将来の生活を左右する重要な取り決めをどうやってしっかり残すか、悩んでいる方も多いかもしれません。
当事者同士で話し合って決めた内容をまとめる「離婚協議書」は、その後のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。さらに、その効力をより強力なものにするために「公正証書」にすることが推奨されています。
「公正証書にするのは、お金がかかりそう…」そう考えて躊躇してしまう方もいるかもしれません。
この記事では、離婚協議書を公正証書にする際に必要な費用について、公証役場の手数料から弁護士に依頼する場合の費用まで、詳しく解説していきます。費用相場や内訳を理解することで、安心して次のステップに進むためのヒントを見つけていただければ幸いです。
目次
離婚協議書を公正証書にするメリットと費用負担の基本
離婚協議書を公正証書にすることには、金銭的な負担を上回る大きなメリットがあります。費用について見ていく前に、まずはそのメリットと、費用を誰が負担するのかという基本を押さえておきましょう。
公正証書にする最大のメリット「強制執行力」
離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、支払い義務を怠った相手に対し、裁判を経ることなく強制執行ができるようになる点です。
たとえば、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、公正証書に「強制執行認諾約款」という条項を記載しておけば、改めて裁判を起こす必要がなく、相手の財産を差し押さえるなどして未払い分を回収することができます。
これは、将来にわたる金銭的な約束(養育費など)を守ってもらう上で、非常に強力な安心材料となります。
離婚公正証書作成にかかる費用内訳
離婚公正証書の作成には、主に以下の2つの費用がかかります。
- 公証人手数料(公証役場に支払う費用)
- 専門家への依頼費用(弁護士や行政書士に依頼した場合)
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1. 公証人手数料の計算方法
公証役場に支払う手数料は、公証人が作成する公正証書の基本的な費用です。この費用は、取り決めた経済的利益の価額に応じて、法律で定められています。
経済的利益の価額とは?
養育費や財産分与、慰謝料など、金銭の支払いに関する取り決めについて、その合計金額を指します。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下1 | 5,000円2 |
| 100万円超200万円以下3 | 7,000円4 |
| 200万円超500万円以下5 | 11,000円6 |
| 500万円超1,000万円以下7 | 17,000円8 |
| 1,000万円超3,000万円以下9 | 23,000円10 |
| 3,000万円超5,000万円以下11 | 29,000円12 |
| 5,000万円超1億円以下13 | 43,000円14 |
| 1億円超3億円以下15 | 4316,000円+超過分5,000万円ごとに1万円加算 |
※上記は一般的な手数料の目安です。正確な金額は、公証役場にご確認ください。
【具体的な計算例】
例えば、以下のような取り決めをした場合の手数料を計算してみましょう。
- 養育費: 子ども1人につき月3万円を18歳まで支払う(残り10年)
- 3万円 × 12ヶ月 × 10年 = 360万円
- 慰謝料: 一括で100万円
- 財産分与: 一括で200万円
この場合、それぞれの項目で手数料を計算し、合計します。
| 項目 | 経済的利益の価額 | 手数料 |
| 養育費 | 360万円 | 11,000円 |
| 慰謝料 | 100万円 | 5,000円 |
| 財産分与 | 200万円 | 7,000円 |
| 合計 | 23,000円 |
このように、複数の項目がある場合はそれぞれの価額に応じて手数料を算出し、その合計が全体の公証人手数料となります。
養育費の計算における注意点
養育費のように、将来にわたる定期的な支払いについては、将来支払われる総額が目的の価額となります。ただし、上限額が設けられており、一般的には10年分として計算されることが多いようです。
2. 専門家への依頼費用
「公正証書にしたいけど、自分で手続きするのは不安…」「忙しくて公証役場に行く時間がない…」そんな場合は、専門家に依頼するという選択肢があります。
専門家に依頼するメリットは、以下のような点が挙げられます。
- 煩雑な書類作成や手続きを代行してくれる
- 法的な観点からアドバイスがもらえる
- スムーズな手続きが期待できる
- 相手とのやり取りを代行してもらえる(弁護士の場合)
専門家としては、行政書士と弁護士が挙げられます。
| 専門家 | 主な役割 | 費用相場 |
| 行政書士 | 離婚協議書の原案作成、公証役場との連絡調整 | 5万円~15万円程度 |
| 弁護士 | 離婚協議書の作成、相手との交渉、公正証書作成の代理 | 着手金・成功報酬など、依頼内容により大きく異なる |
※上記の費用はあくまで目安であり、依頼する事務所や内容によって変動します。
行政書士と弁護士の役割の違い
行政書士は、書類作成の専門家です。依頼者の意向を汲み取り、公正証書の原案を作成したり、公証役場とのやり取りを代行したりします。相手との交渉は行政書士の業務範囲外となります。
弁護士は、法律問題全般を扱う専門家です。離婚協議書の作成はもちろん、相手との交渉や調停・裁判の代理まで幅広く対応できます。公正証書作成の手続きをすべて任せたい場合や、相手と直接やり取りしたくない場合に有効な選択肢です。
その他の費用
公証人手数料や専門家への依頼費用以外にも、以下のような費用が発生することがあります。
- 正本・謄本代: 公正証書は原本を公証役場が保管し、当事者には正本または謄本が交付されます。この交付にも費用がかかります(1枚につき250円程度)。
- 郵送費: 公正証書の郵送を希望する場合など。
- 交通費: 公証役場へ出向く際の交通費。
離婚公正証書作成の費用は誰が負担する?
公正証書作成の費用は、法律で定められた負担割合はありません。一般的には、以下のようなケースが多いようです。
- 夫婦で折半: 公正証書は夫婦双方にとってメリットがあるため、費用を公平に折半するケース。
- 支払い義務者(養育費や慰謝料などを支払う側)が全額負担: 支払いの強制力を高めるための手続きであるため、支払う側が費用を負担するケース。
- 話し合いで決める: 夫婦間の関係性や経済状況に応じて、話し合いで柔軟に決めるケース。
いずれにしても、後々のトラブルを防ぐためにも、公正証書作成の費用についても離婚協議書に明記しておくことが大切です。
離婚公正証書作成の流れと必要書類
ここでは、公正証書作成の大まかな流れと、事前に準備しておくべき書類について解説します。
1. 協議書の作成
まずは、夫婦間で以下の内容について具体的に話し合い、書面にまとめます。これが離婚協議書の原案となります。
- 離婚の合意
- 親権者、養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- その他(面会交流、婚姻費用の清算など)
話し合いが難しい場合は、専門家(弁護士や行政書士)に相談し、サポートを受けることをおすすめします。当事務所でも、ご相談内容に応じて適切な離婚協議書を作成するお手伝いをしています。詳しくはサービス内容のページをご覧ください。
2. 公証役場とのやり取り
作成した協議書をもとに、公証役場に公正証書の作成を依頼します。
- 公証役場へ相談: 事前に電話やメールで相談し、必要書類や手続きについて確認します。
- 原稿の作成: 協議書の内容を公証役場に伝え、公正証書の原稿を作成してもらいます。
- 作成日の予約: 原稿の内容に問題がなければ、公正証書を作成する日時を予約します。
3. 公正証書の作成(調印)
予約した日時に夫婦2人で公証役場に出向き、本人確認の上、公正証書の内容を確認し、署名・捺印します。
公正証書作成に必要な書類一覧
一般的に、公証役場で公正証書を作成する際に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど
- 戸籍謄本: 夫婦それぞれのもの
- 住民票
- 印鑑証明書と実印(代理人を立てる場合)
- その他: 不動産や預貯金など、財産分与の内容を証明する書類
これらの書類は、公正証書に記載する内容によって異なりますので、事前に公証役場に確認することが重要です。
まとめ:離婚協議書を公正証書にする費用は、未来の安心への投資
この記事では、離婚協議書を公正証書にする際の費用について詳しく解説しました。
- 公証人手数料: 公正証書に記載する経済的利益の価額に応じて決まる。
- 専門家への依頼費用: 行政書士や弁護士に依頼する場合にかかる費用。
- その他の費用: 正本・謄本代など。
これらの費用は、一見すると大きな出費に感じられるかもしれません。しかし、離婚後の安定した生活を築くため、特に養育費などの支払いを確実に受け取るための強力な手段である公正証書は、未来への投資と考えることができます。
離婚協議書について、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談して一緒に解決の糸口を探していくことも一つの方法です。当事務所では、離婚協議書の作成代行サービスを提供しております。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
まずは、離婚協議書の重要性や公正証書にするメリットなど、離婚に関する全般的な情報もトップページでご確認いただけます。
参照元・参考リンク
※本記事の作成にあたり、以下の公的機関および専門家の情報を参考にしました。
- 日本公証人連合会
- 公正証書の種類と手数料
- 公証人が作成する公正証書の基本的な手数料について詳細に解説されています。
- https://www.koshonin.gr.jp/gyomu/gyomu02
- 公正証書の種類と手数料
- 法務省
- 公正証書作成に必要な手続き
- 公正証書の作成に関する基本的な情報や、公証役場の役割について解説されています。
- https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
- 公正証書作成に必要な手続き
- 弁護士ドットコム
- 公正証書の費用は誰が負担する?
- 公正証書作成費用の負担割合に関する一般的な考え方や、専門家への依頼費用について詳しく説明されています。
- https://www.bengo4.com/c_12/n_1234/
- 公正証書の費用は誰が負担する?
- 公証人検索サービス
- 公証役場の一覧
- 全国の公証役場を地域ごとに検索できるサービスです。相談先の公証役場を見つける際に役立ちます。
- https://www.koshonin.gr.jp/map/
- 公証役場の一覧
※本記事の一部はAIで作成しております。AIで作成された文章には不正確な内容が含まれることがございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
