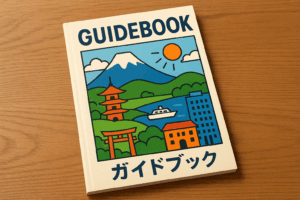共同親権制度の真実:子どもの未来とどう向き合うべきか

共同親権制度とは何か
共同親権制度の基本的な概要
共同親権制度とは、両親が離婚後も子どもの親権を共有する制度のことを指します。現在の日本では、離婚後の親権は通常どちらか一方の親が単独で持つ「単独親権」が採用されています。しかし、共同親権では、離婚後も両親が子どもの養育や教育について共に責任を持ち、子どもの最善の利益に沿う形で意思決定を行います。この制度の導入により、子どもが両親それぞれと継続的に関係を築ける可能性が高まるとされています。
単独親権との違い
単独親権制度と比較すると、共同親権制度には大きな違いがあります。単独親権では離婚後、どちらか一方の親が親権を持ち、もう一方は子どもの日常的な決定に関与できなくなることが一般的です。一方で、共同親権では、両親が離婚後も同等の権利と義務を持ち続け、たとえば子どもの進学先や医療の選択などの重要な決定を協議して行う必要があります。この違いにより、親の役割や関与度が大きく変わり、子どもの生活にも直接影響を与える点が特徴です。
共同親権が導入される背景
共同親権制度が注目されている背景には、離婚後も子どもが両親と良好な関係を維持する必要性や、子どもの最善の利益を重視する国際的な潮流があります。また、現在の単独親権制度では、親権を失った親が子どもと疎遠になるケースが多いことや、養育費の取り決めや面会交流が滞る原因となるとの指摘もあります。さらに、モラハラや不倫が関与した複雑なケースにおいても、親が双方ともに責任を持てる仕組みが求められていることも、この制度を推進する理由の一つとなっています。
諸外国の共同親権事情
共同親権制度はすでに多くの国々で採用されています。たとえば、欧米諸国では共同親権が一般的であり、特にスウェーデンやフランスでは離婚後の共同養育を基盤とした法律が存在します。これらの国では、親同士がしっかりとコミュニケーションを取り、子どもの心身の健全な発達を支えるためのルールと基盤が整っています。また、多くの国では、共同親権のもとで養育費や面会交流に関する取り決めも法的に透明化され、子どもの福祉が第一に考慮されています。このような先進国の事例は日本にとっても重要な参考になるでしょう。
共同親権と養育費の関係
共同親権が導入されると養育費はどう変わる?
共同親権が導入されても養育費の支払い義務そのものは変わりません。養育費は未成熟子の健全な成長を支えるための重要な資金であり、親の離婚や共同親権の選択にかかわらず、法的に求められるものです。ただし、制度上の変更により、両親が子どもと関わる時間や経済的負担がより公平に分配される可能性があります。共同親権では親が共同で子どもの成長に責任を持つため、それに応じた養育費の取り決めが必要となります。
養育費の新たなルールと取り決め方
共同親権の導入に伴い、法定養育費制度が創設され、養育費の取り決めがより明確化される方向に進む見込みです。具体的には、養育費債権の優先性が高まり、親が養育費を支払わない場合の差押え手続きや情報開示が簡素化されます。また、離婚調停の場や家庭裁判所で、子どもの人数や年齢、両親の収入に基づいた適正な金額を算出する仕組みが整備されることが期待されています。こうした改革は、養育費の未払い問題を軽減するために重要となるでしょう。
養育費の未払い問題とその対策
日本では養育費の受給率が低く、母子世帯で28%、父子世帯ではわずか9%にとどまっている現状があります。そのため、未払い問題の対策が急務とされています。共同親権の導入を機に、養育費の先取特権が付与されるとともに、未払い時に差押えがしやすくなるなど、法的手続きの強化が進められる予定です。また、法律相談窓口の活用や、養育費の保証機構の設立が進展することも期待されています。こうした仕組みにより、子どもが安心して育つ環境を整えることが目標です。
不倫やモラハラが関与する場合の例
不倫やモラハラが離婚原因として関与する場合でも、養育費の支払い義務は免除されることなく、通常どおり発生します。不倫した配偶者が親権を持つ場合でも、子どもの健全な成長を支えるため、もう一方の親が養育費を支払う必要があります。たとえば、モラハラを理由に離婚し、親権を取得した例では、養育費として月額3万7000円が20歳まで支払われる取り決めが調停で成立した事例があります。このように、親自身の問題ではなく、子どもの利益を最優先に考える姿勢が求められます。
共同親権が子どもに与える影響
子どもの意思と共同親権の関係
共同親権制度では、子どもの意思が重要視される場合があります。離婚した両親が共同で子育てに責任を持つ中で、子ども自身がどのような生活を望むかを尊重することが求められます。例えば、親権に関する話し合いが進められる際、子どもが家庭裁判所で意見を述べる機会も設けられるケースがあります。ただし、子どもの意思を尊重する一方で、その意思が環境や親の影響を受けやすい点も考慮する必要があります。
親同士の合意が求められる場面の影響
共同親権では、子どもに関する重要な事項について親同士の合意が必要となります。例えば、学校の進路や医療に関する意思決定には、両親の話し合いが不可欠です。しかし、離婚の原因がモラハラや不倫といった深刻な対立であった場合、合意形成がスムーズに進まないことも考えられます。このような状況では、離婚調停や家庭裁判所の介入が必要となり、時間や精神的負担が増える可能性があります。
心理的・経済的負担への考慮
共同親権による親同士の協力体制は理想的ですが、親にとって心理的および経済的負担が増加する可能性があります。例えば、共同親権を維持するためには、離婚後も親同士が連絡を取り続ける必要があり、これが心理的ストレスとなることがあります。また、親権を共有している場合であっても、養育費の負担は発生します。両親が互いに支え合う仕組みを築けない場合、その経済的負担が直接子どもの生活や教育に影響を与える可能性も懸念されています。
親の対立が子どもへ及ぼす弊害
親同士の対立が続く場合、それが子どもへ与える影響は深刻です。不倫やモラハラが離婚の原因である場合、その事実が子どもに知られることで心理的負担が増大する可能性があります。また、親同士の対立が家庭環境の不安定さを生むことで、子どもの精神的な発達に悪影響を及ぼすケースも考えられます。共同親権制度を導入するにあたっては、子どもにとって最善の利益が確保される環境を整えることが重要です。
今後の課題と解決策
法整備の現状と今後の展望
現在、日本では離婚後の親権は基本的に単独親権制度が採用されていますが、共同親権を選択できるようにする民法改正が進められています。この改正案は2024年に成立予定であり、2026年5月までには施行される見込みです。共同親権の導入により親権が分担されることで、親同士が協力して子どもの最善の利益を追求する環境が整うことが期待されています。
一方で、法整備に伴い養育費の取り決めや履行をより確実にするため、法定養育費制度の創設や養育費債権への先取特権付与といった新ルールも導入される予定です。これらの取り組みは単なる制度の変更にとどまらず、経済的な支援体制の強化を目指しており、未成熟子の健全な成長を支えるために重要な展開と考えられます。
家庭裁判所の役割と調停の対応
離婚時における親権や養育費の取り決めは、家庭裁判所による調停が重要な役割を果たしています。共同親権制度が導入されることで、離婚後も両親が共同して親権を行使する場面が増えると予想されますが、それに伴い親同士の合意が求められる問題がさらに複雑化する恐れがあります。特にモラハラや不倫といった事情が絡む場合は、調停が難航するケースも少なくありません。
このため、家庭裁判所は適切な判断基準を策定し、捜査機関や専門家と連携しながら、親権者間の意見調整を円滑に進める体制を整える必要があります。親子関係の維持と子どもの福祉を最優先とする観点から、公平かつ柔軟な対応が求められています。
市民の意見と社会の在り方
共同親権制度をより実効性のあるものにするためには、法律の整備だけでなく、社会全体としての理解と支援が欠かせません。親権や養育費に関する意識調査を実施することで市民の声を収集し、それを基に具体的な制度設計を行うことが重要です。また、離婚調停や家庭問題に関する教育を万遍なく広めることも必要です。
さらに、養育費の支払い率向上に向けた社会的キャンペーンを展開し、支払い義務の認識を醸成することが課題のひとつです。不倫やモラハラを理由に離婚した場合でも、子どもの養育費は不可欠であることを再確認し、親権を持つ側と持たない側が共に子どもの将来に責任を持つ社会の在り方を目指すべきです。
子どもの未来を守るためにできること
共同親権制度の導入には、子どもの最善の利益を優先する観点が不可欠です。両親が離婚した後も、子どもが安定した環境で育つことができるよう、親の対話を促進する方策を考える必要があります。例えば、養育費の自動徴収制度や子どもに焦点を当てた面会交流支援サービスを拡充することが挙げられます。
また、共同親権に関する啓発活動を通じて、親同士の対立を回避し、子どもの福祉を優先する意識を共有する環境を整えることが求められます。家庭問題を抱える家庭へアクセスしやすい相談窓口を設けるとともに、専門家や支援団体との連携を強化することで、個々の事情に応じた適切な支援が可能になることが期待されています。